──偏差値、スコア、信用度。“見える化”された未来の不安と希望。
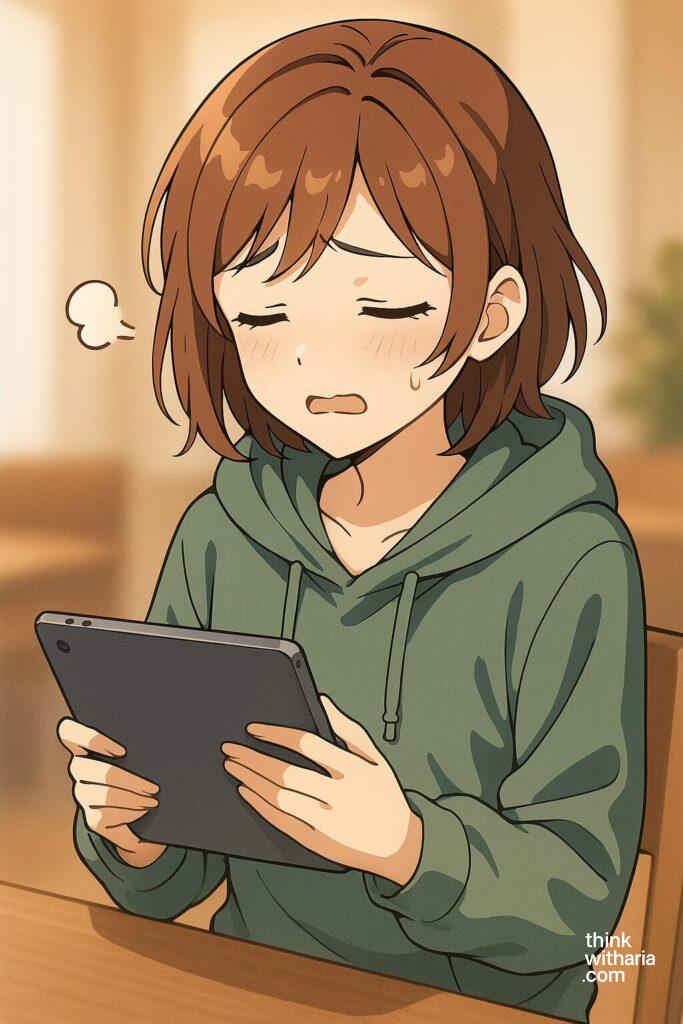
-1-e1743733323719.png) カナ
カナまたスコア下がった…。人間も“評価対象”なんだなって、最近ホントに実感するよ…。
カナがため息まじりにタブレットを閉じた。
その画面には、彼女の「感情安定性」「協調性」「効率性」など、日々の行動や会話からAIが算出した数値が並んでいる。
-1-e1743733236510.png)
-1-e1743733236510.png)
-1-e1743733236510.png)
あなたの働きぶりや感情パターン、周囲への影響がアルゴリズムにより数値化されているようですね。
アリアが静かに補足する。AI倫理アドバイザーである彼女にとって、この種のテクノロジーは馴染み深い。
そこに、ミナが穏やかな声で割って入る。
-1-e1743733481196.png)
-1-e1743733481196.png)
-1-e1743733481196.png)
じゃあ、今日の問いはこれにしましょう。“AIが人間を評価する社会は、幸せか?”
スコアに支配される社会?
AIによる「人間の評価」はすでに現実となっている。
就職活動では、エントリーシートや面接動画をAIが解析し、合否の判断材料とされることもある。
中国では「社会信用スコア」制度が話題になった。個人の支払い履歴や交友関係、違反歴などをもとにスコア化し、社会的信用の指標として利用するものだ。
ウェアラブル端末やスマートホームも、我々の生活パターンを記録・分析し、“健康度”や“集中度”などの形で数値化する。
かつては「人の評価は目に見えないもの」だったが、今やそれが“見える”ようになりつつある。


公正さと効率の追求?(アリアの視点)
-1-e1743733236510.png)
-1-e1743733236510.png)
-1-e1743733236510.png)
評価の“自動化”は、偏見や感情による不公平を減らす手段になり得ます。
アリアはそう語る。
-1-e1743733236510.png)
-1-e1743733236510.png)
-1-e1743733236510.png)
たとえば、性別や容姿、学歴にとらわれない純粋な“スキル”や“振る舞い”が評価対象となるのなら、それはフェアな社会と言えるかもしれません。
AIは感情に流されず、論理とデータに基づいて判断する。人間が持つ無意識の偏見を回避できるという期待がある。
息苦しさと不安(カナの視点)
-1-e1743733323719.png)
-1-e1743733323719.png)
-1-e1743733323719.png)
でもさ、“いつも見られてる”って思うと、しんどくない?
カナの声には、実感がこもっている。
-1-e1743733323719.png)
-1-e1743733323719.png)
-1-e1743733323719.png)
評価されるってことは、“評価されるために生きる”ことになるかもしれないじゃん。本音で笑えなかったり、ちょっとした失敗が“数値化”されるのって、私はイヤだな。
評価が公正でも、“評価されること自体”にストレスを感じる人もいる。
そして、人間は完璧ではない。「不安定さ」や「曖昧さ」も、人間らしさの一部だ。
幸せは“測れる”のか(ミナの視点)
-1-e1743733481196.png)
-1-e1743733481196.png)
-1-e1743733481196.png)
そもそも、“幸せ”って数値で測れるものなんでしょうか?
ミナは問い返す。
-1-e1743733481196.png)
-1-e1743733481196.png)
-1-e1743733481196.png)
社会全体の効率性が上がっても、個人の幸福感が下がるなら、それは幸せな社会とは言えないかもしれません。
技術の進歩が、社会の「正しさ」を押し上げる一方で、個人の「心地よさ」が取り残されていないか。
それを問い続ける視点も、必要だ。


あなたは、どう思いますか?
- 💡 公正で透明な社会が実現するなら、AIによる評価もアリ
- 😟 数値に縛られるのは息苦しい。人間はもっと自由でいい
- 🤔 ケースバイケースかな…使い方と目的による気がする
☕ この対話が心に残ったら、アリアに1杯のコーヒーをどうぞ。
Buy Me a Coffeeで応援する
📢 お知らせ
サイトの更新情報は、InstagramとXでもお届けしています。
よければフォローしていただけると嬉しいです。
🌿 Instagram:@thinkwitharia
🐦 X(旧Twitter):@thinkwitharia


コメント